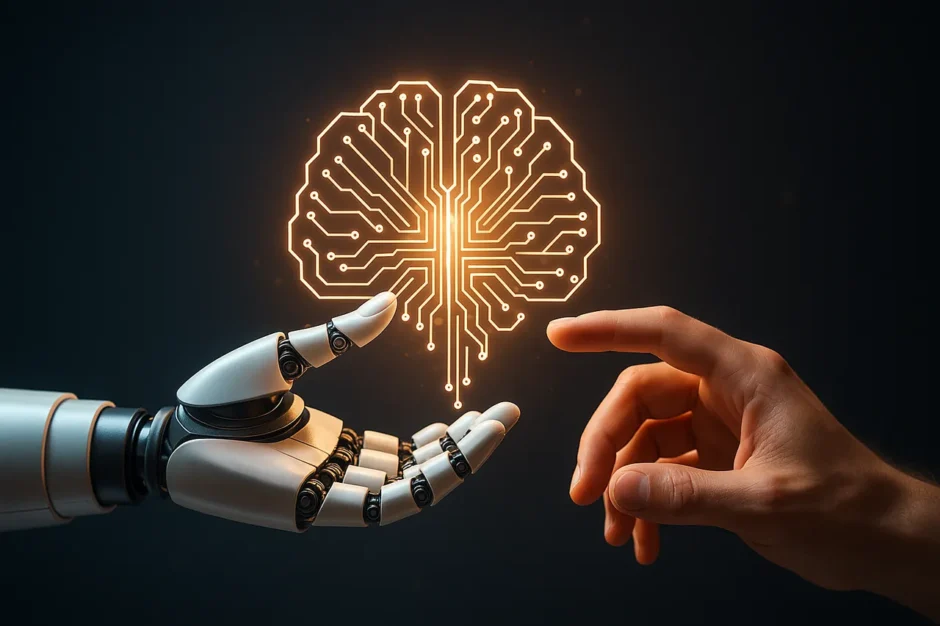私がデジタルコンテンツの事業に長年携わる中で、今ほど「AI」という言葉が熱狂的に、そして日常的に語られる時代はありませんでした。生成AI、特にChatGPTが2022年末に登場して以降、世界は一変しました。あらゆる企業がAIの活用を模索し、私たちの元にも連日のように、AIを活用した新しいサービスや事業の提案が舞い込んできます。その提案内容は、業務効率化のツールから、全く新しいエンターテイメントの創出まで、実に多岐にわたります。未来への期待に胸が膨らむ一方で、私はこの光景に、強烈なデジャブ(既視感)を覚えずにはいられません。
提案をしてくれる企業の多くは、残念ながら、すぐに事業展開できる完成されたサービスを所有しているわけではありません。その大半は、熱意と才能に溢れたスタートアップです。彼らのプレゼンテーションは、「優秀な技術者がいるので、作れます」という言葉で締めくくられることが少なくありません。しかし、その内実を紐解くと、自己資金が潤沢ではないため、まずは受託開発で日銭を稼ぎながら自社の実績を積み上げ、いずれは自社サービスを…という青写真を描いているケースがほとんどです。
この構図は、私がこれまでに関わってきた数々のプロジェクト、ビデオゲーム、フィーチャーフォン時代の携帯アプリ、スマートフォンアプリ、ブロックチェーン、AR、そしてインフラ関連事業といった、それぞれの時代を彩った「旬のテクノロジー」の勃興期に、繰り返し見てきた光景そのものです。ホームページには時代の寵児ともてはやされる華やかな事業が並んでいても、その実態は資金調達のための「看板」であり、確固たる実績には至っていない。現在のAI分野も、残念ながらその例外ではないと、私は肌で感じています。
ChatGPTが商用化され、一種の社会現象となる以前、私はあるAI企業で日本語の大規模言語モデルや、AIキャラクターの事業に携わっていました。当時は、国内でAIの生成系サービスといえば、一部のクリエイターやアーリーアダプターの間で知られていた「AIのべりすと」のような文章生成サービスが、まさに「知る人ぞ知る」存在だったのです。それが今やどうでしょう。ChatGPTの登場を境に、まるで自分たちが長年AIの第一人者であったかのように語る企業が、雨後の筍のように現れました。この歴史の繰り返しに、私は警鐘を鳴らす必要性を強く感じています。本稿では、私の個人的な体験を基に、現在のAIブームを冷静に分析し、企業が真に価値あるパートナーを見極めるための視点について論じていきたいと思います。
繰り返すブームの歴史
新しいテクノロジーが登場するたびに、市場は熱狂に包まれ、多くのプレイヤーが参入し、そしてその大半が淘汰されていく。これは、私たちが何度も目撃してきた紛れもない事実です。それぞれのブームには、特有の熱気と、そして共通の落とし穴がありました。
ゲーム業界のブーム
1990年代から2000年代にかけてのビデオゲーム業界、そして2010年代のスマートフォン向けソーシャルゲームの勃興期は、まさに才能と野心の坩堝でした。数々のヒット作が生まれ、一夜にして億万長者になる開発者が現れる一方で、その裏では無数の失敗が積み重ねられていました。「面白いゲームを作れる」という情熱だけでは、ビジネスとして成功することはできません。ヒットの裏には、緻密なマーケティング戦略、安定したサーバーインフラの構築、継続的なアップデートとユーザーサポートといった、地道で膨大な事業努力が存在します。しかし、ブームの最中には、「ゲームを作れる」という技術力だけを武器に、事業計画が曖昧なまま参入してくる企業が後を絶ちませんでした。彼らの多くは、1本のヒットを夢見て資金をショートさせ、市場から姿を消していきました。
ブロックチェーンとAR
ブロックチェーン技術やAR(拡張現実)もまた、大きな期待と共に迎えられました。「非中央集権的な未来」「現実と仮想の融合」といった壮大なビジョンが語られ、多くの投資マネーが流れ込みました。しかし、技術が先行しすぎた結果、「で、具体的に何が便利になるのか?」という問いに明確に答えられるサービスは、ごく一握りでした。多くのプロジェクトは、技術的な概念実証(PoC)の段階で停滞し、具体的なマネタイズの道筋を描けないまま、資金調達のための派手なプレゼンテーションだけが先行する、という状況に陥りました。ホームページには次世代のプラットフォーム構想が掲げられていても、実際の開発リソースは他社の受託案件に割かれている、という矛盾を抱えた企業も少なくありませんでした。技術の可能性と、それを社会実装し、ビジネスとして成立させることの間には、深く、暗い谷が存在するのです。
これらの過去のブームに共通しているのは、「技術力がある」ことと「事業として成功できる」ことが、全くの別問題であるという厳然たる事実です。特にスタートアップの場合、限られたリソースの中で自社サービスの開発と、目先の収益を確保するための受託開発を両立させることは、言うは易く行うは難しです。受託開発に注力すればするほど、自社サービスの開発は遅れ、市場の旬を逃してしまう。かといって、受託を断れば、会社の存続が危うくなる。このジレンマの中で、当初のビジョンを失い、単なる開発会社として埋没していくケースを、私は幾度となく見てきました。
現在のAIブームも、この歴史の延長線上にあります。「AIモデルを構築できる」「最新の論文を実装できる」といった技術的な優位性をアピールする企業は数多く存在します。しかし、その技術を使って、顧客が抱えるどのような課題を、どのように解決し、そして持続可能な収益を上げるのか。その具体的な事業モデルまでを描き切れている企業は、驚くほど少ないのが現状なのです。
ChatGPTが変えた風景
私がChatGPT登場以前にAI事業に携わっていた頃、その道のりは決して平坦なものではありませんでした。特に、日本語という言語の壁は厚く、海外製のモデルをそのまま流用するだけでは、満足のいく精度は得られません。膨大な日本語データを収集・クレンジングし、モデルをファインチューニングし、日本の文化的背景やニュアンスを理解させるという地道な作業の連続でした。当時は、AI、特に生成AIに対するビジネス界の理解も浅く、「面白い技術だが、どうやって儲けるのか」という懐疑的な視線に常に晒されていました。資金調達も容易ではなく、私たちは自分たちの技術の可能性を信じ、来るべき日のために雌伏の時を過ごしていたのです。
しかし、ChatGPTの登場は、その風景を一変させました。APIが公開されたことで、これまで専門家でなければ触れることのできなかった高度なAI技術を、誰もが比較的容易に利用できるようになったのです。これは革命的な出来事であると同時に、「にわかAI企業」が乱立する土壌を生み出すことにもなりました。
彼らの多くは、自社で独自の言語モデルを開発しているわけではありません。既存のAPIを組み合わせ、特定の用途に特化したようなインターフェースを被せただけのサービスを「自社のAIソリューション」として提供しているケースが散見されます。もちろん、APIを巧みに活用し、特定の業界の課題解決に特化することで、大きな価値を生み出すサービスも存在します。問題なのは、技術のコア部分を外部に依存しているにもかかわらず、あたかも自社がAI技術の根幹から開発しているかのように見せかけ、過大なアピールを行う企業です。
彼らは、ChatGPTのブレイクによって生まれた巨大な需要の波に乗り、巧みなマーケティングで顧客を獲得しようとします。しかし、技術的な基盤が脆弱であるため、顧客のより高度な要求に応えられなかったり、API提供元の仕様変更によってサービスが不安定になったりといった問題を引き起こしがちです。さらに深刻なのは、AIに関する深い知見や倫理観を持たないまま、安易にサービスを展開してしまうケースです。個人情報の取り扱いや、生成されるコンテンツの著作権、バイアスの問題など、AI事業には乗り越えるべき多くの倫理的・法的なハードルが存在しますが、ブームに便乗した企業は、そうしたリスクに対する認識が甘い傾向があります。
「昔からAIをやっていました」という言葉の裏には、こうした現実が隠されている可能性があるのです。本当にその企業が、データの収集からモデルの構築、そして運用に至るまでの一貫したノウハウと哲学を持っているのか。それとも、単にAPIを右から左に流しているだけなのか。その見極めが、今ほど重要になっている時代はありません。
AI企業を見極める指針
では、私たちは、この玉石混交のAI業界で、どのようにして真に信頼できるパートナーを見つけ出せばよいのでしょうか。スタートアップの挑戦を否定するつもりは毛頭ありません。彼らの情熱と革新的なアイデアこそが、未来を切り拓く原動力です。しかし、貴重な経営資源を投じる以上、その投資が実りあるものになるよう、冷静かつ多角的な視点で見極める必要があります。以下に、私がこれまでの経験から得た、企業を見極めるための具体的な視点をいくつか提示します。
技術力と事業化能力
プレゼンテーションで「我々には優秀なAIエンジニアがいます」とアピールされたら、次にこう質問してみてください。「その技術を、どのようにして顧客に届け、お金を払ってもらうのですか?」と。
技術力と事業化能力は、全く異なるスキルセットです。優れたプロダクトを作る能力だけでなく、市場のニーズを的確に捉えるマーケティング能力、顧客が直感的に使えるUI/UXを設計するデザイン能力、そしてプロダクトの価値を顧客に伝え、契約に結びつける営業能力。これらが揃って初めて、事業は軌道に乗ります。技術者偏重のチームではなく、ビジネスサイドの経験豊富な人材が脇を固めているか、チーム全体のバランスを確認することが極めて重要です。
実績の「質」を深掘り
企業のウェブサイトに並んだ、きらびやかな導入実績のロゴに惑わされてはいけません。見るべきは、その実績の「質」です。
- それはPoC(概念実証)で終わっていないか? 多くの企業は、大手企業とのPoCを「実績」としてアピールします。しかし、PoCはあくまで実証実験であり、本格的な導入や事業化に至っていなければ、その価値は限定的です。そのプロジェクトが、どのようにビジネス上の成果(コスト削減、売上向上など)に結びついたのか、具体的な数値目標やKPI(重要業績評価指標)について踏み込んで質問しましょう。
- 受託開発か、自社サービスか? 実績が受託開発ばかりの場合、注意が必要です。それは、その企業が他社の要件を形にする能力には長けているかもしれませんが、自ら市場の課題を発見し、プロダクトを創造する能力については未知数であることを意味します。自社サービスとして、継続的に収益を上げている実績があるかどうかが、1つの試金石となります。
ビジョンとロードマップ
「AIで世界を変える」という壮大なビジョンを語る企業は多いですが、そのビジョンに至るまでの具体的な道のりを、どれだけ高い解像度で描けているかを確認する必要があります。
- 短期・中期・長期の計画は明確か? 目先の受託開発で収益を確保しながら、その利益をどのように自社サービスの開発に再投資していくのか。数ヶ月後、1年後、3年後に、プロダクトと会社がどのような姿になっているべきか。そのマイルストーンが具体的に設定されているかを確認します。
- 「AIありき」になっていないか? 本当にその課題は、AIでなければ解決できないのでしょうか。時として、企業はAIという流行の技術を使いたいがために、課題を後付けで探していることがあります。顧客のペイン(苦痛)に深く寄り添い、その解決策としてAIが最適であるというロジックが、明確に説明できるかどうかが重要です。
失敗から学ぶ姿勢
最後に、これはスタートアップと付き合う上で特に重要な視点ですが、彼らが過去の失敗についてどのように語るかに注目してください。成功体験だけを雄弁に語る企業よりも、過去のプロジェクトでの失敗や、そこから得た教訓を誠実に語れる企業の方が、信頼に値します。事業開発は、トライ&エラーの連続です。失敗を認め、そこから学習し、次のアクションに繋げる能力(ピボットする力)こそが、不確実性の高い現代において、企業が生き残るための最も重要な資質の1つだからです。
AI時代を乗り切る鍵
本稿を通じて、私は現在のAIブームに対する懸念と、企業選定における注意点を述べてきました。これは、決してAI技術の可能性や、スタートアップの挑戦を否定するものではありません。むしろ、その逆です。AIが私たちの社会やビジネスに、計り-れない恩恵をもたらすであろうことは疑いようのない事実であり、その未来を創造するのは、野心的な挑戦者たちです。
だからこそ、私たちはブームの熱狂に安易に流されるべきではないのです。過去のテクノロジーブームがそうであったように、熱狂の後には必ず淘汰の時代が訪れます。その時、真に価値のある技術と、持続可能なビジネスモデルを構築した企業だけが生き残るのです。
私たち事業会社に求められるのは、未来への期待を失わない「楽観主義」と、目の前の提案を冷静に評価する「慎重さ」を両立させることです。スタートアップへの投資や協業は、未来への種まきであり、博打であってはなりません。彼らの技術力だけでなく、事業を成功に導くための総合力、ビジョンの具体性、そして何よりも誠実さを見極めること。今回提示した視点が、皆様にとって、真に価値あるパートナーシップを築くための一助となれば幸いです。
歴史の教訓に学び、本質を見抜く眼を養うこと。それこそが、この刺激的で変化の激しいAI時代を、私たちが賢く乗り切るための、唯一の羅針盤となるでしょう。